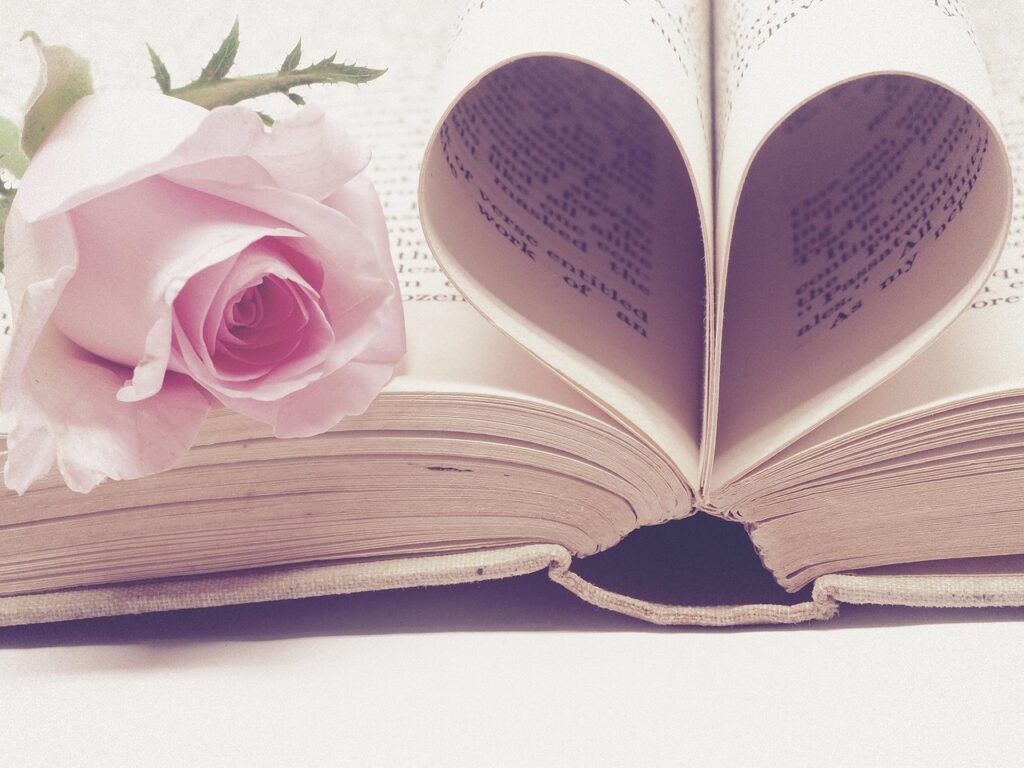
皆さん、素敵な恋はできていますか?
些細なことで相手を想うようになり、誰もが羨むような素敵な恋をすることもあれば、ただ心が傷つくばかりで自分の気持ちを抑え込んでいる方もいらっしゃることでしょう。
今回は平安時代に書かれた恋に関する和歌を紹介していきたいと思います。
ぜひ平安時代の人々に想いを馳せてみてみてください。
1. 紀貫之(きのつらゆき)
『古今和歌集』の編者の一人であり、恋の歌を多く残しました。
人はいさ心も知らずふるさとは 花ぞ昔の香ににほひける
現代語訳
人の心は変わるものだけれど、故郷の桜の花は昔と変わらず美しく香っている
2. 小野小町(おののこまち)
絶世の美女とされ、恋の歌を多く詠んだことで有名です。
思ひつつ寝ればや人の見えつらむ 夢と知りせば覚めざらましを
現代語訳
あなたを想いながら眠ったら夢に出てきた。夢だと知っていたら、目覚めたくなかったのに
3. 在原業平(ありわらのなりひら)
『伊勢物語』の主人公とされる人物で、情熱的な恋の歌を詠みました。
ちはやぶる神代も聞かず竜田川 からくれなゐに水くくるとは
現代語訳
神話の時代にも聞いたことがない。竜田川の水が紅葉で赤く染まるなんて
4. 藤原定家(ふじわらのさだいえ)
『百人一首』を編纂した歌人で、恋の歌も多く残しています。
来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに 焼くや藻塩の身もこがれつつ
現代語訳
来ない人を待ち続ける私は、松帆の浦の静かな夕暮れに燃える藻塩のように、身も焦がれている
5. 紫式部(むらさきしきぶ)
『源氏物語』の作者であり、恋の歌も詠みました。
めぐり逢ひて見しやそれともわかぬ間に 雲隠れにし夜半の月かな
現代語訳
久しぶりに会えたのに、それが夢だったのか現実だったのか分からないうちに、夜の月は雲に隠れてしまった
6. 和泉式部(いずみしきぶ)
恋多き女性として知られ、情熱的な恋の歌を多く残しました。
あらざらむこの世のほかの思ひ出に 今ひとたびの逢ふこともがな
現代語訳
私はもうすぐこの世を去るでしょう。その前に、もう一度あなたに会いたい
7. 清少納言(せいしょうなごん)
『枕草子』の作者であり、恋の歌も詠みました。
夜をこめて鳥のそらねははかるとも よに逢ふ坂の関は許さじ
現代語訳
夜が明ける前に鶏の鳴き声を偽っても、逢瀬を阻む関所は決して許してくれないでしょう
8. 藤原道綱母(ふじわらのみちつなのはは)
『蜻蛉日記』の作者であり、夫との切ない恋愛を綴った歌を残しました。
風吹けば沖つ白波たつた山 夜半にや君がひとり越ゆらむ
現代語訳
風が吹くと沖の白波が立つが、その「たつ」という名の竜田山を、あなたはこの夜中にひとりで越えているのでしょうか
9. 紫式部(むらさきしきぶ)
『源氏物語』の作者であり、恋の歌も詠みました。
逢ふことの絶えてしなくはなかなかに 人をも身をも恨みざらまし
現代語訳
あなたに会えない日々が続くなら、いっそ完全に会えないほうがいい。そうすれば、あなたを恨むことも、自分を責めることもないのに
10. 菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)
『更級日記』の作者であり、恋の歌も詠みました。
夢にだに見ゆるものならば うつつにも逢ふよしをがな
現代語訳
夢の中でさえあなたに会えるなら、現実でも会う方法があればいいのに
~終わりに~
平安時代の恋の和歌は、現代でも多くの人の心を打つ美しさがありますね。
私たちと同じように誰かを一途に想い、心寄せる人を待ち続ける。なんとも素敵ですね。
恋人にかかわらず家族や友人、今に至るまで自分のために尽力してくれた人々、ともに笑いあったかつての仲間たちに感謝しなければいけませんね。
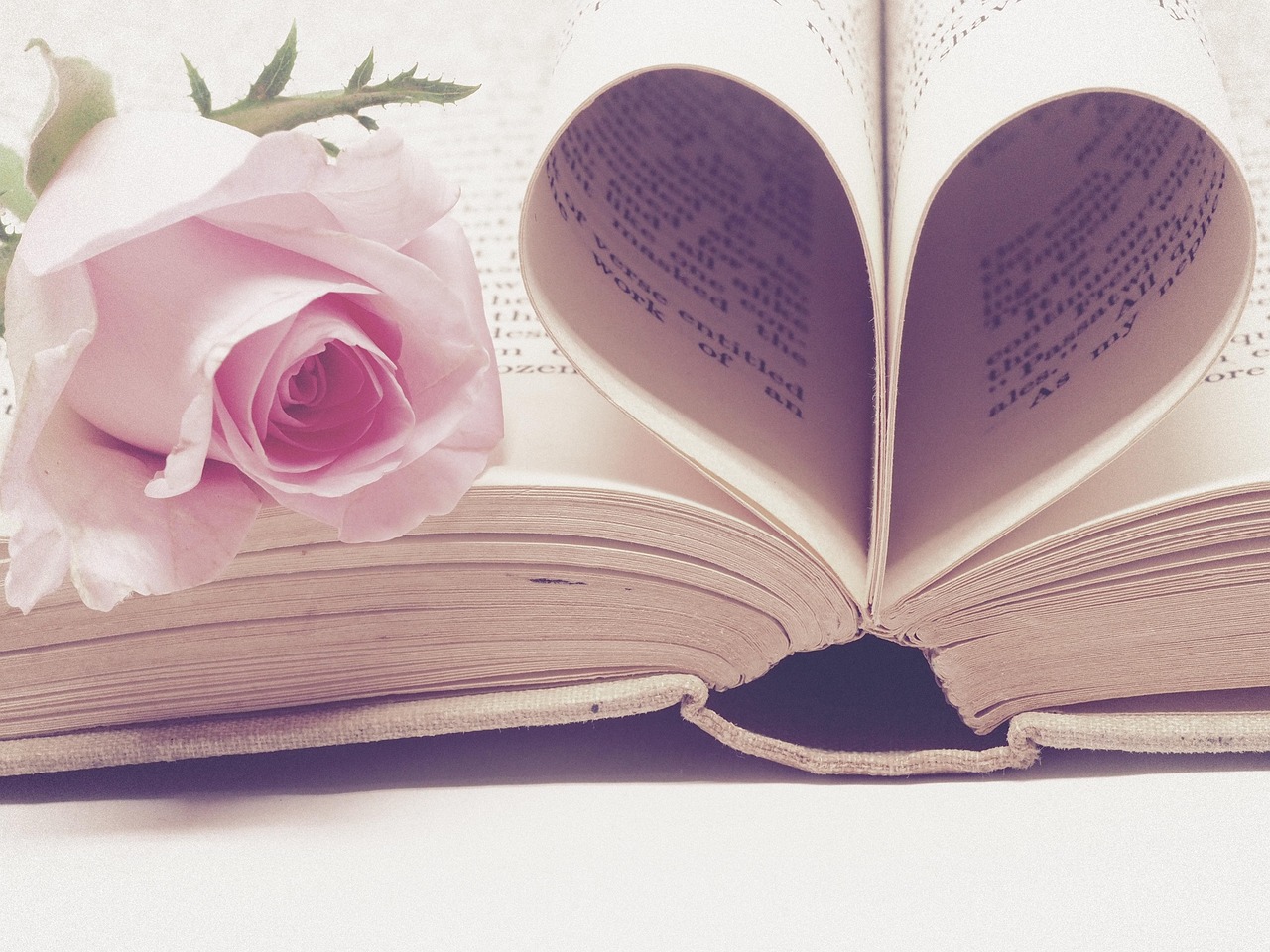

コメント